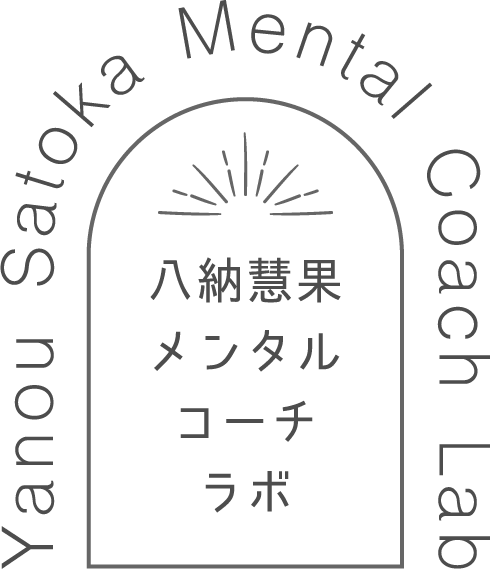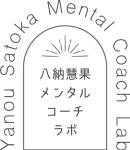「うちの子、算数が苦手で…」 そんな悩みを抱えている親御さん、多いのではないでしょうか?
あるお母さんの実話です。
お子さんの毎日の宿題がまるで修行のようだったと話されます。特に、小学1年生の計算カード(「5+2」「8−3」など)は地獄そのもの。リングでまとめられたカードを1枚ずつめくり、裏の答えを確認する…それを50回以上繰り返すなんて、そりゃ退屈に決まっています。
最初のうちは、このお母さんも横についていましたが、ある日、席を立った隙に、子どもがこっそり枚数をごまかしているのを目撃。「これはもう、やり方を変えないとダメだな」と思ったそうです。
まず取り入れたのは、図を使う方法。「5+2」なら、○を5個、隣に○を2個描いて、視覚的に理解できるようにしました。指を使うのも効果的です。こうして間違いは減りましたが、やっぱり「つまらない」ことに変わりはありません。
そこで、子どもが大好きな「かるた」を応用してみました。
- 計算カードを机に並べる(最初は枚数少なめ、徐々に増やす)。
- 子どもが1枚ずつ取り、答えを言う。
- 裏返して答え合わせ。
- 正解ならリングに通す。
これがうまくいきました!全てのカードが目に見え、答えるたびに枚数が減っていくので、ゲーム感覚で取り組めるようになりました。ところが問題も発生。親がずっと付き添う必要があり、監視役になってしまう…。これはお互いにストレスです。
そこで、次の改良をされました。
- 机に並べるのは同じ。
- 口頭ではなく、ノートに答えを書く。
- 自分で答え合わせをし、正解なら赤丸、不正解なら訂正。
最初は1列終わるごとにチェックしていましたが、すぐに慣れ、自分で管理できるようになりました。「宿題をやった」という証拠がノートに残るので、達成感もアップ。自分で花丸をつけたり、「やったね!!!」とコメントを書いたり、楽しみながら取り組むようになりました。
結果、「やらされる宿題」から「自分で進める宿題」へと変わり、計算スピードもアップ!
子どもにとって「目に見える形」にすることが、どれだけ大切かを実感しました。宿題に苦戦している親御さん、一度試してみてはいかがでしょうか?