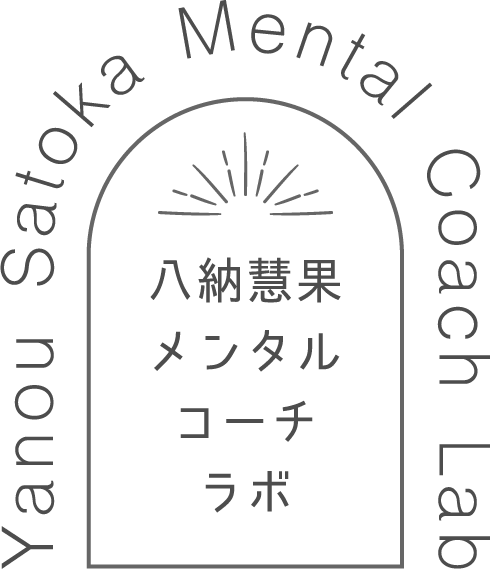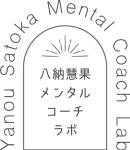クライエントのRさんから、「娘のピアノの練習時にどうしても怒ってしまう」という相談を受けました。
以下に、その時のやりとりをまとめています。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
7歳の娘さんは昨年12月にピアノを始め、家ではお母さんがそばで見守っています。お母さんも昔ならっていたぶん、「こうすれば上手くなるはず」とつい口が出ます。自分が苦労したやり方を子どもに当てはめたくなる、早く結果を見たい、レッスン代の元を取りたい――こうした気持ちが、きつい言い方や無理な練習につながることは、どの家庭でも起こりがちです。
娘さんは新しい曲に向き合うたびに、「最初はむずかしい→同じところを何度もやる→指が覚える」という流れを、体で学んでいます。うまくいかない所がつづき、気持ちがしぼみそうになると、習い始めの本を自分で取り出し、やさしい曲を一曲ひき切ってから、元の練習にもどります。これは、だれにも教わらず身につけた“気持ちの立て直し”で、「私、できるんだ」を思い出す上手な工夫です。ここに、娘さんの強み(自分で元気を回復できる力)がはっきり見えます。
一方で、お母さんの悩みは「そばにいると感情的になる」「でも離れると、娘は正しい弾き方がわからない」という点です。このズレをほどくために、つぎの提案をしました。
1)時間を切る:
「10分教える→5分休む」を1セットに。砂時計やタイマーを使い、休憩はかならず区切る。熱くなる前にいったん離れるしくみです。
2)役割を分ける:
教える時間は“先生役”(姿勢・指の形・ゆっくり通す)。休憩後は“応援役”(よかった所を3つ伝える)。「ここがよくなったね」「音がそろってきたね」など具体的に。
3)気持ちの回復を道具化:
行き詰まったら“初級本で1曲”。ひけたらシールを貼る、ハイタッチをするなど、見えるごほうびで「できた」を積み上げる。
4)お母さん自身をいたわる:
休憩のはじめに深呼吸を3回、肩を回す。「今日もここまでやれた、えらい」とお母さんが自分に対して、心の中でつぶやく。親の余裕は、そのまま子どもの集中に映ります。
多くのおやごさんが本当に求めているのは、「正しく教えること」よりも「家で毎日つづけられる形」です。完ぺきな指導より、“回しやすい流れ”があること。たとえば、①今日の目標は1つにしぼる(「左手のリズムだけ」)、②うまくいかなければ“初級本にいったん避難”、③最後は必ず得意なフレーズで終える――この3つなら手間はふえず、子どもの「またやりたい」を守れます。
このやり方にしてから、娘さんは休憩中でも「このまま続けてもいい?」と自分から手を動かし、自然に上達が加速しました。お母さんが“がんばりの温度”を調整できるようになったからです。
家での練習でいちばん大切なのは、正解をさがすことより「明日も座れる空気」を守ること。娘さんの“立て直す力”を信じ、短いサイクルで「できた」を積み重ね、親子それぞれをやさしくねぎらう――それが、長く伸びる土台になります。