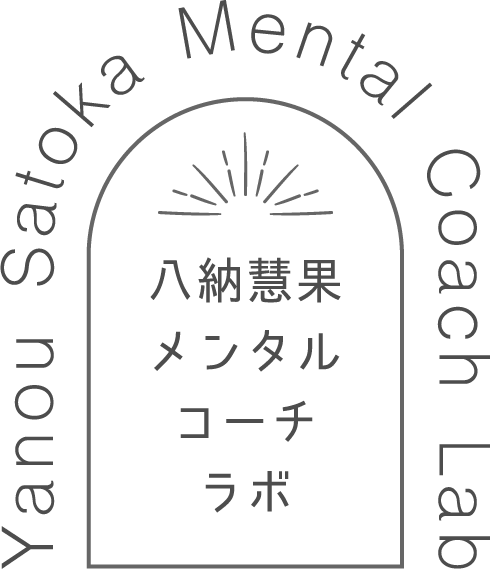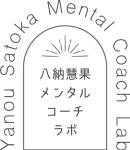子どもが使っていた椅子の上に、かばんが置いてある。
その椅子をこれから使いたい。
子どもはすぐそばにいる。
あなたなら、どうしますか?
多くの人は、さっと手を伸ばして動かすか、
「かばん動かして」とだけ声をかけると思います。
私も、ずっとそうしてきました。
でも、娘が通っていた幼稚園の先生の対応は、全く違いました。
参観日のとき、子どもたちのかばんを動かす必要が出ました。
そのとき先生は、一人ずつ目を見て、こう言ったのです。
「○○ちゃん、ここを使うから、かばんをそっちに動かしてもいい?」
ただ“動かして”と言うのではなく、
・理由を伝える
・子どもの気持ちを確かめる
この二つを、毎回ていねいにしていました。
しかも、それは特別な日だけではありません。
席を移動するとき。
机の場所を変えるとき。
朝の会の前に座ってほしいとき。
どんな場面でも、先生は必ず理由を添えて、お願いの形で伝えていました。
その姿を見たとき、胸がつまるような感覚がありました。
後で理由を聞くと、先生はこう言いました。
「子どもは小さな変化にも敏感なんです。
かばんの場所が違うだけで固まる子もいるし、
理由が分からないと、とても不安になる子もいます。」
その言葉を聞きながら、私は自分のことを思い返しました。
大人同士では、こんなことはしません。
人のかばんを勝手に動かしたり、
理由もなく「どいて」と命令することは、まずありません。
でも、相手が自分の子どもになると、
この配慮が抜け落ちることがあるのです。
実際、家の中でも心当たりがいくつもあります。
いつものコップの位置を勝手に変えてしまうと、
子どもはじっと固まって動けなくなることがあります。
お気に入りのぬいぐるみを“片づけたつもり”で場所を変えると、
子どもは必死で探しながら泣きそうになることがあります。
大人の目から見れば「そんなことで?」と思うようなことでも、
子どもにとっては、安心の土台が揺らぐ大きな出来事なのです。
そして、その気持ちは大人と同じです。
自分のデスクの物が勝手に動かされていたら嫌ですし、
理由がないまま席を変えられたら、落ちつきません。
ただ、子どもはその気持ちをまだ言葉にできないだけなのです。
だからこそ、
「動かしてもいい?」
「こういう理由なんだけど、どう思う?」
とひと言添えることには大きな意味があります。
その声かけは、
「あなたの持ち物は大事に思っている」
「勝手に決めないよ」
というメッセージになります。
こうした小さな積み重ねが、子どもに
「尊重されている」という感覚を育てます。
そしてその感覚は、のちのち
「嫌なことは嫌と言える」
「自分の気持ちを落ちついて伝えられる」
という力につながっていきます。
幼稚園の先生の姿を見て、私は深く反省しつつ、
同時に「今日から変えればいい」と思いました。
子育ては、気づいたときがスタートです。
完璧ではなくていい。
ただ、“してもいい?”という一言を足すだけで、
子どもの表情はふっとやわらかくなります。
そのやわらかい表情こそ、
「大事にされている」と感じた証なのだと思います。