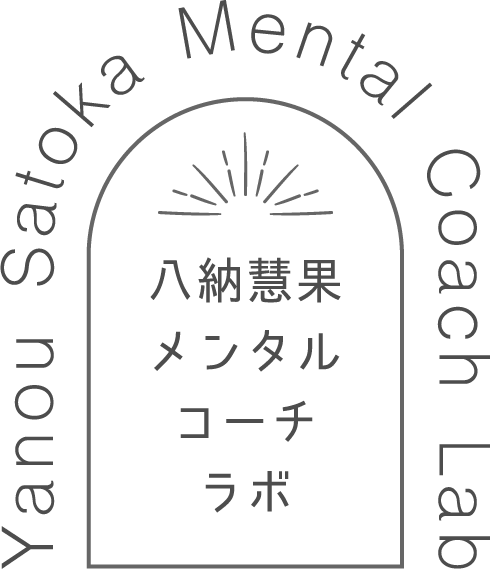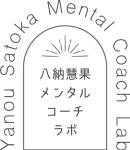日本には昔から、「以心伝心」「あうんの呼吸」「腹芸」といった“察する文化”が根付いています。
「言わなくてもわかる関係こそ理想」という空気感も、私たちの中には根強くあります。
たしかに、言葉を交わさずとも気持ちが一致した瞬間は、「通じ合えた!」という感動があります。
けれど、それは宝くじのようなもので、現実には滅多に起こらない奇跡に近いこと。
それでも私たちは、大切な人との関係の中で、「きっとわかってくれるはず」「こんなに一緒にいるんだから、言わなくても伝わってるよね」と期待してしまう。そしてその期待が裏切られた時、「どうしてわかってくれないの?」「こんなに頑張ってるのに」と、心がもつれていくのです。
特に夫婦や親子といった“近しい関係”では、この「察してほしい」「察するべきだ」という無言のプレッシャーが大きくなりがちです。けれど、本来、どれだけ近い関係でも、心は別々。だからこそ、気持ちは「言葉にして伝える」しかないのです。
とはいえ、感情を言葉にするのは、簡単なようで実はとても難しいこと。日本語は感情を表す言葉が豊富なはずなのに、自分の気持ちにぴったり合う表現を探すのは、思った以上に骨が折れます。
しかも、言葉選びを間違えば、意図しない誤解や衝突を生んでしまうこともある。
だからこそ、私たちは“言わない”という選択に逃げがちになるのです。
でも、関係が近くなるほど、言葉を交わすことを怠ってはいけません。
むしろ、関係を良好に保つためには、「めんどうくさい」時こそ、きちんと言葉をかけ合うことが必要です。
うまく伝わらないこともあるでしょう。
ときには、言いすぎてしまって後悔することもあるかもしれません。
でも、そんなときこそ、素直に「ごめんね」と言えることが、関係を深めるチャンスになります。
完璧に伝えることよりも、伝えようとする姿勢と、その後の誠実な対応こそが大切なのです。
人との関係は、「わかってくれなかった」とがっかりする前に、「伝えようとしたか?」「伝わらなかったとき、どう向き合ったか?」を自分に問いかけることで、大きく変わっていくのです。
近しい人との絆を育てるというのは、実は“言葉にする勇気”と“素直に謝る強さ”の積み重ねなのかもしれません。