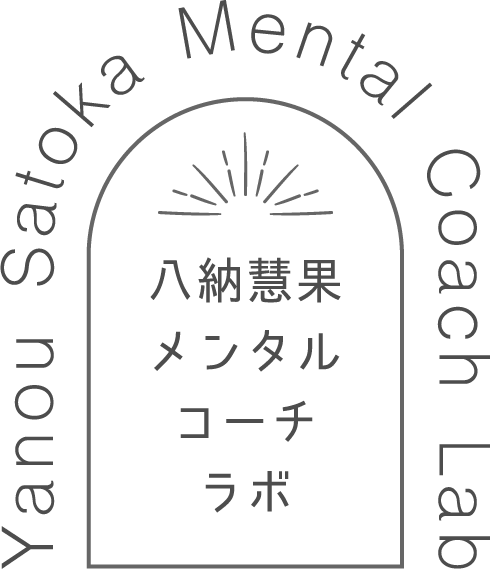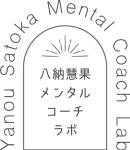「人間関係をよくしたいんです」
と相談に来られる方の多くが、同じ壁にぶつかっています。
「夫がいつも怒ってばかりで気が休まらない」
「子供が何度言っても行動しない」
「職場の上司が高圧的で意見が言えない」
「友人が陰で悪口を言っているようで気が重い」
年齢を重ねるにつれ、人間関係の数が増え、それに比例して悩みも複雑になります。
家庭、職場、ママ友、親戚…と、自分の立場や役割も変化するなかで、関係性のストレスがどんどん積み重なっていくのです。
そんなときに大切な視点が、次の2つです。
まず1つ目は、「相手は変わらないかもしれない」という事実を知ること。
実は、悩んでいるのは“こちら側”だけ、というケースがとても多いのです。
相手はその関係性に多少の不満は感じていたとしても、「困っている」とまでは思っていない。
だから、自ら変わろうとしないのです。
2つ目は、「相手に〇〇してほしい」から、「私がどうする?」に視点を移すこと。
例えば、夫が冷たいなら「夫にもっと優しくしてほしい」ではなく、「私はどう言葉をかけたらいい?」と考える。
子供が動かないなら「もっと自主的になってほしい」ではなく、「私の伝え方に余地はある?」と自問する。
ここで、ありがちな落とし穴があります。
それは、「私が変われば、相手もきっと変わってくれるはず」と期待してしまうことです。
でも、これは“期待”という名の幻想。
たしかに、自分の言動を変えることは素晴らしい行動です。
でも、それを「相手が変わることへの投資」にしてしまうと、変わらなかったときに深く傷ついてしまいます。
たとえば、ある50代の女性は「夫がいつも無口で冷たい。私が家事も気遣いも頑張れば、いつか優しい言葉を返してくれるかも」と努力を重ねました。
でも、夫の態度は変わらず、彼女は「何をしても無駄だった」と自信を失ってしまったのです。
「これだけ頑張ったのに、相手は全く変わらない。やっても無駄なんだ」と思ってしまう気持ちは、とてもよくわかります。報われない思いは、虚しさや怒りとなって心に積もります。
そして、「もう何もしたくない」「関わるのも疲れた」と、すべてを投げ出したくなることもあるでしょう。
けれど、そこで手を止めてしまったら、やはり何も変わりません。
むしろ、自分の中に残るのは「諦めた自分」への後悔です。
実際、先ほどの女性に、話を戻します。
彼女は、何もかも嫌になって、1ヶ月ほど家事も会話も最低限に抑え、家庭内の空気はさらに冷え込みました。
ところが、ある日ふと「私は誰のために頑張ってきたんだろう?」と自問したのです。
そして、「夫の反応ではなく、私は“あたたかい家庭をつくる人”でいたい」と思い直しました。
そこからは、「ありがとう」と伝える、相手の愚痴を黙って聞く、子どもの前で夫の悪口を言わない——
そうした行動を、小さくても“自分の信念”として続けたのです。
すると、数ヶ月後。夫の口からこんな言葉が出ました。
「最近、家が前より落ち着く気がするな。ありがとな。」
大きな劇的変化ではなくても、「関係性の空気」が変わることで、人は少しずつほぐれていきます。
大切なのは、「私はどうありたいか」を軸にすること。
相手がどう反応するかは、期待せず、委ねる。
そうすると、自分の行動が“評価待ち”ではなく、自分自身への納得感に変わります。
人間関係は、変えようとすると難しい。
でも、見方を変えることで、意外なほど風通しがよくなるのです。