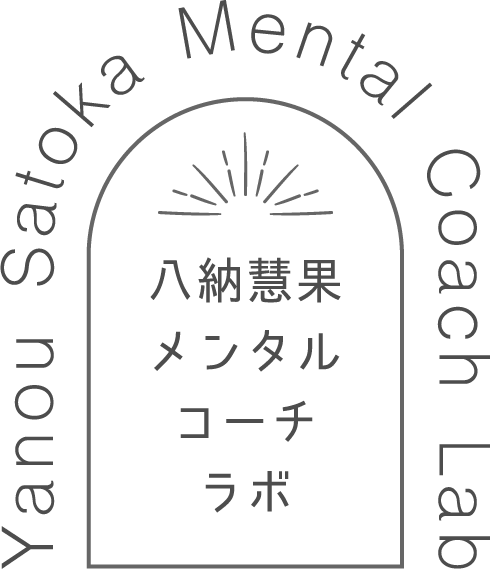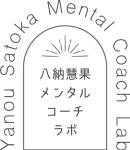娘が通っていた幼稚園では、先生たちは「できなかったこと」ではなく「できたこと」だけに反応していました。
初めてその場に立ち会った時、私は思わず息をのみました。
参観日の会場は、子どもたちの高い声でにぎやかです。
ふだんより興奮して、そりゃ静かになんてできるわけがない。
私は「そろそろ注意の声が飛ぶだろう」と身構えていました。
でも、静かにする声かけはありません。
「お口チャック」も「座りなさい」もない。
なのに、子どもたちは、少しずつ本当に静かになっていくのです。
「あれ?なんで?」
不思議になって視線を向けると、先生がひとり、無言で手遊びを始めていました。
歌もない。声もない。
ただ、そっと手を動かしているだけ。
すると、そのすぐ近くの子が気づき、同じように手を動かす。
その波が静かに広がっていき、気がつくと全員が声もなく手遊びをしていました。
最後は先生が小さく「手はおひざ」とだけ伝える。
そして一言。
「静かに座れています。ありがとう。」
できていない子に目を向けるのではなく、できている子を認める。
ただそれだけで、場が整っていく。
その光景に、私は胸をつかまれる思いでした。
なぜなら、私はずっと反対のやり方をしていたからです。
娘に対しても、そして自分自身に対しても、
“できていないところ”ばかり見つめていた。
仕事でも家でも、つい「もっとできたはず」と自分を追い立てていた。
どれだけがんばっても、「よくやったね」と言えなかった。
達成したはずの自分を、いつも置いてきぼりにしていました。
だからこそ、娘が褒められている姿を見て、
私の中の固くなった部分が少しずつほぐれていきました。
とはいえ、人は急には変われません。
「褒めよう」と思っていても、忙しい毎日の中では忘れてしまう。
つい昔のクセが顔を出す。
そこで私は、生活の中に無理なく落とし込む工夫をしました。
一日ひとつ、
娘や私が“できたこと”をノートに書く。
たった一行でいいので、夜寝る前に書く。
娘のことで「いいね」と思えた日には、カレンダーに小さな◯を書く。
目のつく場所にそれが増えていくと、気持ちまで明るくなる。
そして何より大きかったのは、
“娘が褒められることに慣れている”ということ。
私が忘れるとすぐ気づくのです。
「ママ、今日褒めてないよ?」
「もっと心をこめて言ってほしいな」
あの無邪気なひと言は、私の背中を押してくれました。
(正直、これがいちばん効きます…!)
こうして少しずつ、
「怒るより褒める」が生活のあたりまえになり、
私の中から“自分を責める声”も静かに弱まっていきました。
今振り返ると、
娘に向けた言葉は、そのまま自分にも向けていたのだと思います。
褒める習慣は、子どものためだけじゃない。
一番救われたのは、私自身でした。